最近の小学生のなりたい職業ランキングにYouTuber”ユーチューバー”という言葉が出てくる程、YouTube好きな子どもが増えてきています。
私の子どもも、1歳半頃からYouTubeを見るようになり、最初は「スマホの操作が出来るのすごいなー」なんて思ってました。
でも、最近こちらの記事を読んで、YouTubeはNHKなどの教育テレビと違って、
- 編集にコストがかけられておらず、伝えたいことが不明確もしくは子供にとって不適切
- コンテンツの中で使用する言葉が厳選されていない
などなど、YouTubeによる子どもの悪影響について考えるようになりました。そして、「YouTubeを見るのは止めさせたい」と思いました。
そこで、何とかして子どもの「YouTube」を止めさせようと、昔私が読んだ『伝え方が9割』という本の『7つの切り口』で子どもがYouTubeを見るのを止めさせる方法について考えてみました。
子どもがYouTubeを見るのをやめさせたいと思った
我が家では、子どもが1歳半頃に少しYouTubeを見せたことがきっかけとなり、YouTubeにどっぷりとハマってしまいました。
少し時間が空くと、
「Youtube見るー」
と言って、聞きませんでした。
ひどい時は1時間もスマホのYoutubeを見続けるようになっていました。
子どもがスマホでYouTubeばかり見るので、
「目が悪くなるのでは?」
とか
「言葉の発達が遅くなる、もしくは変な言葉を覚えるのでは?」
とかを気にし始めました。
Googleで検索しても子どもがYouTubeを見続けると、「忍耐力がなくなる」とか「覚える言葉が稚拙」などなど、色んな記事を読みました。
というわけで、なんとかして子どもがYouTubeを見るのをやめさせたいなと思ったわけです。
そんなことを考えていたころに、昔読んだ「伝え方が9割」の本から「YouTubeを止める言葉掛け」を考えたいなと思ったわけです。
“伝え方が9割”とは?

出典:https://matome.naver.jp/odai/2136796747105433201
「ノー」を「イエス」に変える魔法、どう伝えれば相手の「ノー」を「イエス」に変えることができるかが書かれている本です。
2013年に発売され、大人気ベストセラーとなっており、発行部数は50万部を突破し、「伝え方が9割 2」が出版されました。
私も実際にこの本を読みましたが、一番印象的だったのが以下の言葉でした。
こちらから何かをお願いした時に相手の答えを「ノー」から「イエス」に変えるのはしゃべりが上手い/下手の問題ではない。伝え方を知っているか知らないかの違いである。
引用 伝え方が9割
で、本当にそうなのかを自分の子どもで試してみようと思ったわけです。ただ、その前にまずはこの本に書かれていることをご紹介します。
イエスを引き出す基本の3ステップ
ステップ1 自分の頭の中をそのままコトバにしない
ステップ2 相手の頭の中を想像する
ステップ3 相手のメリットと一致するお願いをつくる
イエスを引き出すためのステップは上記の3つです。
確かに好きな相手に対して「デートしてくれない?」と、自分の思いだけを伝えても「ノー」という返事になる可能性は高そうですよね。
それよりも相手の好きな食べ物などを調べてから、「美味しいパスタ屋を知ってるんだけど、どう?」みたいに、相手のメリットを考えたお願いをすれば、「イエス」を引き出す確率は上がりそうですよね。
で、このステップの中で一番難しいのがステップ2「相手の頭の中を想像する」です。
そこで、この”伝え方が9割”の本では、この難しいステップ2のために7つの切り口を用意してくれています。
相手の頭の中を想像するための”7つの切り口”とは
| No | 切り口 | 説明 |
| 1 | 相手の好きなこと | 要望を相手のメリットに置き換える |
| 2 | 嫌いなこと回避 | 要望をやらない場合のデメリットを伝える |
| 3 | 選択の自由 | 2つの選択肢を提示して、どちらか選ばせる |
| 4 | 認められたい欲 | 要望の前に、相手を認めていることを伝える |
| 5 | あなた限定 | 相手にあなたが特別であると伝える |
| 6 | チームワーク化 | 自分も一緒に行動すると勧誘する |
| 7 | 感謝 | 要望の時に一緒に感謝を伝える |
相手の頭の中を想像するための切り口は上記の7つが用意されています。
私の説明力ではこれが限界ですので詳細は書籍をご確認下さい。笑
というわけで今回はそれぞれの切り口で、子どもがYouTubeを止めるための伝え方について考えてみました。
子どもがYouTubeを止めるための伝え方
1.相手の好きなこと
これは簡単かなと思っていたのですが、意外と難しかったです。なぜなら、相手の好きなこと=”YouTube”なので、既に好きなことをやっているからです。
そこで、子どもがYouTube以上に何が好きかを考えて、伝えてみました。
「公園に行こうよー」
「キドキド(kid-o-kid)/ボールハウスに行こうよー」
「スーパーにお菓子を買いに行こうよー」
等々、外にお出掛けしようというものが響きました。
中でも、一番効果的だったのが
「パパと一緒に遊ぼうよー」
でした。
また、伝え方は「パパと遊んでほしいなー」とか「パパと遊んでくれない?」など、下からの姿勢で聞いてみると、しょうがないなーみたいな感じで「いいよー」と言って、YouTubeを止めて遊んでくれました。
なんだか、子どもとの接し方を見直さないといけないなと感じました。
2.嫌いなこと回避
嫌いなこと回避を考えた時、まず私が思いついたのが、「お外で遊べなくなる(好きなことができなくなる)」でした。
そこで、
「目が悪くなって、お外で遊べなくなるよ」
や
「目が疲れて夜寝れなくなって、明日お外で遊べなくなるよ」
などを伝えたのですが、「目が疲れる」ということがあまり理解できていないせいか、あまり響きませんでした。
それよりも、
「YouTubeばっかり見てると、鬼/おばけが来るよー」
というと、すぐYouTubeを見ることをやめました。
ただ、この切り口で気をつけることは、
- 鬼やおばけにビビっているだけで、YouTubeをやめたいとは思っていない
- 子どもがかなりビビるので、少しかわいそう
- 実際には怖いものが家に来ることはないので、適宜変更が必要
の3点です。
特に3点目に関して、我が家での実体験として私が子供に「YouTubeを見てたら鬼がくるよー」と言い続けていたら、ある日突然、「鬼は来ないよー?」と言い出したことがありました。
怖いものは定期的に変更して下さい。
3.選択の自由
子供に選択させるというのは、かなり微妙でした。
「公園に行くか、デザート食べるかどっちがいい?」
→どちらも魅力的なのか、どちらも選んでくれませんでした。
「モモかブドウか、どっち買いに行く?」
→「ブドウ」と即答でした。すぐにはやめませんでしたが、一応買い物に言ってくれました。
「選択の自由」に関しては、あまり有効ではなかったです。選択肢のいずれかに魅力があると、YouTubeをやめてくれるという感じでした。
ただ、これは切り口的には、「相手の好きなこと」と同じですね。選択の自由を与えたから、YouTubeを止めるというわけではありませんでした。
もともと、「決断が得意でない日本人」を利用した言葉作りの手法ですが、YouTubeを見ているという子どもにとって、決断が得意でないということはあまり関係なかったですね。笑
4.認められたい欲
認められたい欲は子どもにありますので、
「○○ちゃんは粘土で遊ぶの上手だから、パパにも教えてー」
などと伝えると、「いいよー」と笑顔で言ってくれることが多かったです。
その他、
「○○ちゃんがお風呂でパパの体洗うの上手だから、一緒にお風呂行こうよー」
「○○ちゃんがお箸上手になったところをパパにも見せてー」
なども有効でした。
5.あなた限定
これは、子供がどこまで意味を理解しているのかわかりませんでしたが、かなり有効でした。
「ママじゃなくて、○○ちゃんと買い物に行きたいなー」
「○○ちゃんのためだけに、ぶどうを用意したから、一緒に食べようよー」
とにかく、自分の娘の限定感が出るように伝えると、すぐにYoutubeをやめることが多かったです。
6.チームワーク化
これはチームワークというよりも、内容が重要だなという感じでした。
「一緒にお風呂に入ろうよー」
は、もともと子供がお風呂好きではないため、反応が悪かったですが、
「一緒に粘土しようよー」
や
「一緒に公園に行こうよー」
などは反応が良く、「いいよー」って感じですぐ食いついてくれました。
7.感謝
感謝についてはまだ子供には響きづらいのかなと思いました。
「いつもお買い物についてきてくれてありがとうね。じゃー、また今日も行こっかー」
などと言っても、特に変わりはなかったです。笑
まとめ「子どもはYouTubeよりも親が好き」
今回、子どもがYouTubeを見るのをやめさせることについて、”伝え方が9割”の本から7つの切り口で考えてみました。
色々やってみて思いましたが、子供に対しては確かに言い方も大事ですが、私が強く感じたのは「子どもはYouTubeよりも親が好き」でした。(当たり前なんですが。。)
結局、YouTubeを見ることになってしまっているのは、自分が子どもとしっかり向き合えていないからだなと感じました。
子どもと遊ぶ時間を確保していかないといけないですね。
それを踏まえて、改めて感じたのが「完全に止める対策」と「一時的に止める対策」は違うのかなと思います。
完全に止める方法と一時的に止める方法は違う
今回、私が「伝え方が9割」の7つの切り口で考えて、子どもがYouTubeを見るのを止めさせたことは全て、短期的な方法(一時的に止める方法)でした。
また、この記事を自分のヨメにも読んでもらったところ、「原因の分析が甘いんじゃないの?伝え方を考える前に、何でそうなってるかを考えたら?」と言われました。
指摘はごもっともで、確かにその通りだなと思いました。(「子どもがYouTubeを見てるのは全部おれのせい?」という言葉が一瞬ちらきましたが、声には出してません。)
やはり、子どもがYouTubeを見ているのを完全に止めさせるためには、親が子どもと遊ぶ時間を確保するようにする、しかないのかなと思った、今日この頃です。
ちなみに、最近は英語の勉強のためにYouTubeをテレビ・ディスプレイで見せるようにしています。詳細はこちらをご覧下さい。

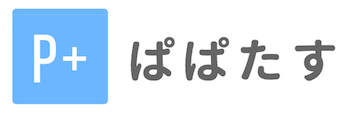


コメント